応召の義務をご存知でしょうか?
応召の義務とは端的に言えば「医師は正当な理由なくして患者さんの診療を断ってはいけない」ということです。
医師法第19条に、医師の応召義務が規定されており、「診療に従事する医師は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを拒んではならない」とされています。
応召義務違反に対して刑事罰は規定されていませんが医師法上、医師免許に対する行政処分はあり得ますし、民事裁判での損害賠償責任が認められた事例も存在します。
何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきとされていました。
でもこれって、かなりあいまいでわかりづらい表現ですよね。
人によって解釈の仕方も違ってくるかもしれません。
医師法に応召義務が規定された当時(昭和23年)は、医療機関相互の機能分担や連係による医療供給体制のシステム化は行われていませんでした。
現代では医療機関相互の機能分化・連携により、良質で適切な医療を効率的に提供する体制が確保されているほか、医療の高度化・専門化もさらに進んでいます。
こうした状況をふまえ、応召義務について時代に即した新たな解釈が必要という意見が高まっていました。
「応召の義務」についての議論が近年活発になった理由の一つには、厚労省が推進する「医師の働き方改革」との関係性があるからです。
応召義務による医師の過剰労働を避けつつ、かつ地域の医療提供体制の確保を目指す厚労省。
医療の現場からのもっとわかりやすい具体例を提示してほしいというニーズにも合わせて、厚労省は2018年より「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」で検討を重ね報告書をまとめ、2019年12月25日の厚労省医政局長通知で応招義務についての法的整理に至りました。
「患者を診察しないことが正当化される事例」は、緊急対応が必要な場合か否か、診療時間・勤務時間内か否かの4パターンに分けて整理しています。
①緊急対応が必要で時間内
医療機関・医師の専門性・診察能力等を総合的に判断して、「事実上診療が不可能と言える場合」にのみ正当化される。
② 緊急対応が必要で時間外
応急的に必要な処置を取ることは望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。
③緊急対応が不要で時間内
患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要はあるものの、緊急対応が必要な場合と比べて、正当化される理由は緩やかに解釈される。
④緊急対応が不要で時間外
即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
ただし、 時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが望ましい。
また、これまでの厚労省通知からは「正当な事由にあたるもの/あたらないもの」として以下の項目が挙げられていますのでご参考まで。
「正当な事由」 にあたるもの
- 医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合
- 休日夜間診療所、休日夜間当番医制など休日夜間診療体制が敷かれている場合、休日夜間診療所、休日夜間当番院などを受診するよう指示すること(ただし応急措置を施さないと患者の生命、身体に重大な影響が及ぶ場合においては、応召義務が発生します)
「正当な事由」にあたらないとされたもの
- 医業報酬が不払(悪質な場合を除く)
- 特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師
- 天候の不良等
- 標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病の診療を求められた場合
今回の通知は現場において、医療従事者からも受診する患者さんからもわかりやすいものであると思います。
今回の通知をきっかけに応召義務についての認識が広く浸透し、よりよい医療サービスの供給体制づくりができると期待します。

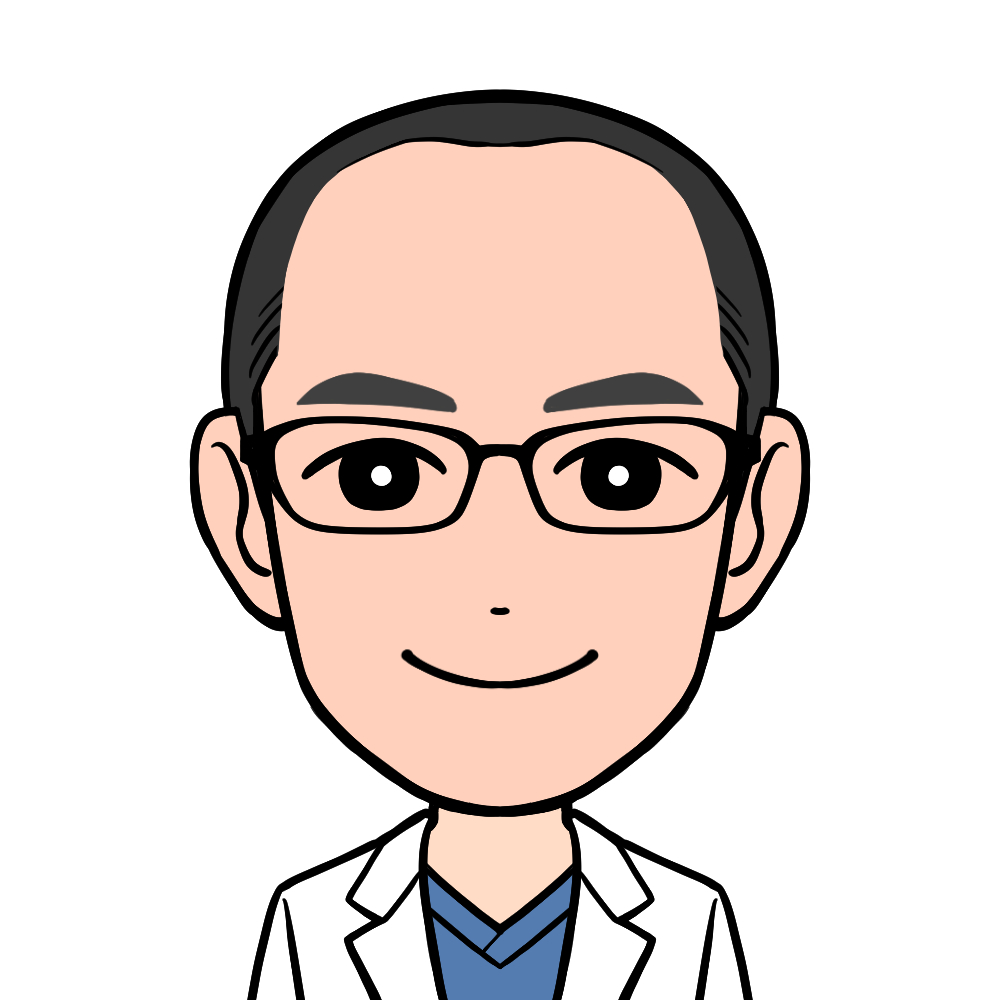








コメント